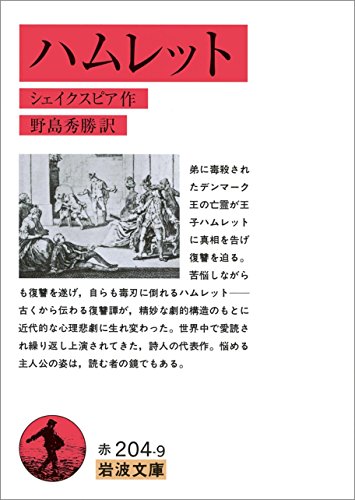ハムレット シェイクスピア作 野島秀勝訳
デンマーク王国の城に最近亡霊が出るという。しかもそれは亡き先代ハムレット王の亡霊だ。ある日噂を聞きつけた息子、ハムレット王子はその真意を汲みとるべく亡霊に向かい合う。亡霊からは現世への恨みが述べられる。王は毒殺されたのだ。犯人はハムレット王子の叔父にあたり、現国王のクローディアス。彼は兄を殺し、その妻を娶り王位の座に着いたのだ。ハムレット王子が復讐を誓うことで運命の歯車は動き始める。
今更いうまでもないシェイクスピア悲劇の一つ。とはいえ恥ずかしながら今まで劇場で観たことはないし、読んだこともなかった。つまりぼくのシェイクスピア初体験はこれである。絵画の方ではミレーのオフィーリアに痺れた思いがあるので、その意味ではもっと早く読んでおけばよかった。絵の感じ方も変わるだろう。
この本は脚本なので舞台の上は自分の頭で想像するしかないが、そこがむしろ楽しい読書体験であった。とはいえ歴史に詳しいわけでもないので、ディティールはイメージできない。なんとんくベルサイユの薔薇っぽいイメージで読んでいたが、たぶんこれは違うのだろう。それでもなかなか楽しめる。それは物語の中に時代を問わない普遍的な要素があるからだろう。
ウィットに富んだ小気味のいいトークが心地よい。しかし、そのなかに様々な感情が溢れる。怒りや悲しみだけでなく、友情や愛もある。狂気さえも。舞台の台詞であるのだが、どこかほんとうに生きた人間くささがある。
ときに短いフレーズに心奪われる。アフォリズムというやつか。「生きるべきか死ぬべきか。それが問題だ」はもちろんとして、ハムレットの独白はなにかぼくを強く惹きつけるパワーがあった。
繰り返し読むべきだと感じた一冊。時代背景などを学べばもっと楽しんで読めるだろう。生きて人生をもっと学び、ぼく自身が成長すれば、イメージ舞台の上に感じるものも変わってくるはずだ。人生のお供になる一冊だ。